「……風見さん」
「は、はい」
幸成の顔が目の前にあった。
「どうしたの、ぼんやりして。そろそろ戻るよ。午後には橋立にも回るんだからね」
「はい……ごめんなさい、ちょっと、ぼーっとしてしまって」
幸成だけでなく、ガイドも澪の顔を覗き込んでいる。
「ごめんなさい、本当に大丈夫です」
頭を下げながら、澪はあたりを確かめた。着物姿の商人も船乗りも、そして走り回っていた子どもたちもいなかった。そして、右の掌に感じていた熱も消え失せていた。
「それじゃあ、案内はここで」まだ心配そうな顔をしているガイドが言った。「この先もまだ船主の家だったところは続いているんですが、一般のお宅になっているんで、見学はここまでになってるんですよ」
「はい……わかりました」
その後、澪たちはスタッフに挨拶をするため、再び右近家に寄った。
「先ほどお伺いした、船箪笥を触っていた人のことですけど、他になにか気になったことありましたか?」
右近家を出る間際、澪は思い立って受付の女性に聞いてみた。すると、彼女ではなく、横にいたガイドが「あ、そういえば」と口を開いた。
「最初にあの人を案内した時ね。そこの八幡丸を見せながら説明してたんですよ」
ガイドは入口すぐの囲炉裏端に置かれた、八幡丸の大きな船模型を指さした。
「そういえば、お客さんたちには八幡丸の説明、ちょっと省略しちゃいましたね。今、詳しく話すから待ってて」
いちど奥に引っ込んだガイドが、額装された大きな写真を抱えて戻ってきた。
「これが八幡丸の写真です。磯前神社に絵馬として奉納されていたものです」
それはセピア色の写真だった。
帆を下ろして停泊中のようだが、甲板いっぱいに満載された荷物と、小さいが船乗りたちの姿も写っている。
「ずいぶん綺麗に撮られた写真ですね」
「えぇ、明治に入ってからのものですから。それでね、あの人にこれを見せながら話をしたんです。八幡丸の最期を」
「最期……?」
「はい。明治三十七年、日露戦争が始まった年、この八幡丸は中村家の安静丸とともに、北海道沖でロシアの水雷艇に撃沈されたんです」
「え、そんな……」
「その頃はもう海運は蒸気船に取って代わられていたんですが、北前船の歴史が終わった象徴的な事件として語り継がれているんですよ」
「北前船の……最期……」
澪が呟くと、ガイドは寂しそうに微笑んだ。
「そんな話をしてたら、あの男の人ね、なんだか涙ぐんでたように見えたんですよ。いや、暗いしね、私の見間違いだったかもしれないんですけど。ここに戻ってきたら、ふと思い出しちゃって」
「……はい。ありがとうございました」
澪たちは右近家を出た。ちょうど昼食時だったので、幸成の提案で、屋敷のすぐ前、元々右近家の離れだった建物を改装した「観光案内所どっときたまえ」に入ることにした。奥では食事や喫茶が楽しめるようになっている。
自分で選んだパスタが運ばれてきたが、澪はしばらく手をつけなかった。
「風見さん」
「はい」
「とりあえず食べちゃったら? その後で話を聞かせてよ。さすがにもういいでしょ?」
「……はい」
パスタの味はよかったが、なかなか食は進まず、結局、半分ほど残してしまった。
「実は昨日の敦賀からなんですけど」
幸成に促される前に、澪は自分から口を開いた。
「あの高燈籠の前で不思議な体験をしたんです。土崎の土蔵で刻磁石に触った時に似ていました。海が目の前に迫ってくる感じになって……さっきの船主通りでも似たようなことがあったんです。田辺さんやガイドさんの姿が消えて、着物姿の人たちがたくさん見えました。あの通りがとても賑わっていて、たぶん、北前船で繁栄していた頃だと思います」
澪が一気に吐き出すように話すのを、幸成は黙って聞いていた。
「それで、昨日の敦賀も今日ここでも共通していたことがありました。右の掌が焼けるみたいに熱くなったんです」
「右の掌……あぁ」幸成はすぐに理解したようだ。「あの土蔵で刻磁石を触った……」
「はい、だと思うんです。異変の前や最中、右の掌に熱を感じていました。それから、声が聞こえてきたんです」
「声?」
「はい、それが……」
食後の珈琲が運ばれてきたので、会話は一時中断した。
「に、会いたい」
「ん?」
「たぶん、最初になにかあると思うんですけど、途中からしか聞こえなくて。誰か……『に、会いたい』という言葉です。不思議な響きで、男の人の声か女の人の声かもわかりません」
「その言葉というのは、それだけ?」
「はい」
「うーん」と唸り、幸成は腕を組んだ。
「その幻みたいのを見たのは、きっと刻磁石の影響かもしれない。信じられない話だけど、もうこうなったらねぇ」
「ええ」と澪もうなずいた。自身であの不思議なビジョンを連日見た今となっては、否定をする気にもなれなかった。
「でもさ、風見さん。その声の方はちょっとわからないよ。男か女かわからないっていうのも気になる。ひょっとして、風見さんの心の声なんじゃないの?」
「私の声、ですか……どういう意味です?」
「いや、なんとなくなんだけど、今、会いたいっていうと、風見さんの心の裡から出た声なんじゃないかと思って」
「……北浦さんに、ですか?」
幸成は深くうなずいた。
「確かに、会いたいからこそ、今、こうなってるわけですけど……でも」
と言ってから、澪はしばらく考え込んだ。不思議な光景を見た時のことを思い返してみる。
「私の心の声じゃない気がするんです。どこか遠くから聞こえてくるような……私に呼びかけているのとは違うんですけど……なんて言ったらいいんでしょう? やっぱり、他人の意思みたいなものを感じるんですよ」
「そうか……まぁ、風見さんがそう言うなら、そういうものかと思うしかないけど。ところで、これからどうする?」
幸成の質問の意図がわからず、澪は首を捻った。
「午後は加賀の橋立に移動して取材の予定ですけど」
「いや、そうじゃなくて。今日の午後からのことも関係はあるけど。もう少し先のことだよ。このままじゃ、僕たちは北浦さんの後を追いかけていくだけになるでしょ?」
「あぁ……」
澪にもようやく、幸成が言いたいことは理解できた。
「そこでどうするかって話でさ。確実とはいえないけど、適当に山を張って北浦さんの先を行く……先回りすることもできるよ」
「それはいいです」
澪は即答した。
「北浦さんには会いたいです。会って話をしたいことがたくさんあります。いいえ、それ以上の気持ちも少しはあります。でも……田辺さん、北浦さんは現代に来て、酒田以外の土地はどれくらい知っているんですか?」
「ん? そうだな。北海道の函館と東京には行っているよ。函館には僕が仕事を頼んで行ってもらった。東京は僕が勧めた。現代の日本がどうなってるか理解してもらうには、東京を見てもらうのが、いちばん手っ取り早いと思ったんだ」
「そうですか。他の土地には?」
「うぅん、プライベートのすべてを監視してたわけじゃないからね。ただ旅行が可能な日数、資料館を留守にしていたことはなかったからね」
「そうなんですね。じゃあこの南越前町も、これから行く加賀の橋立も、現代のこの姿になった町は、北浦さんは初めて訪ねる可能性が高いというわけですね。だったら、やっぱり私……」
「……」
「北浦さんの後を追いかけてみたいです。そして、北浦さんが見たものを見て、聞いたことを聞いてみたいんです。そうすることで、なにか見えてくるものがある、そんな気がしてならないんです」
「そうか、わかった」
幸成は笑うと、身軽な動作で立ち上がった。
「じゃあ、さっそく次の土地へ行こうか」
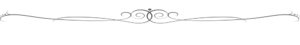
レンタカーで加賀まで移動した澪たちは、加賀温泉駅近くのホテルに荷物を預け、橋立地区へ向かった。
「これから行く橋立も、南越前町の河野と同じ、船主集落なんだ」
「はい」
──橋立を代表する北前船主は、まず、久保彦兵衛。活躍したのは幕末だが、当時の大聖寺藩の財政立て直しに私財を提供するほどの富豪だった。もうひとりは西出孫左衛門。朝倉家の家老の子孫と伝えられるが、代々船乗りとして活躍し、六台目孫左衛門の代に武士の身分に復帰した後も海運業を続け、明治期には久保家を凌ぐ資産を蓄えていた。
これ以外にも橋立には数多くの北前船船主がいた。十八世紀半ばからその数を増やし、十八世紀末には船主三十四名と船頭八名の居住が確認されている。まさに、船主集落だ。
とはいえ、橋立にも明治半ばからの北前船衰退の波は押し寄せた。船主や船頭たちの数は減っていったが、財を蓄えた村であることに変わりはなかった。大正五年に発行された博文館の雑誌「生活」では、隣村の瀬越とともに「日本一の富豪村」として紹介されていたほどだ。
「──同じ船主集落でも、この橋立の最大の特徴は、船主の屋敷が十四軒も現存していて、中心部の百二十戸が加賀市の『歴史的景観整備区域』に指定されていて、かつての船主集落の趣きを色濃く残していることなんだ」
そんな幸成の説明を聞いているうちに、最初の取材先である「北前船の里資料館」に到着した。北前船船主・酒谷長兵衛の屋敷を利用した施設で、現在では加賀市指定有形文化財となっている。
近くに車を停め、澪たちは橋立の土地に立った。
「……あれ」
首を捻った澪を見て、幸成は微笑んだ。
「イメージと違った?」
「あ……はい。富豪村って話を聞いたばかりだったので……なんだか華やかなイメージを持ってました」
普段暮らしている酒田も、決して賑やかではない。だが、この町はどこか時が止まったような、胸に染み入るような静けさがあった。

北前船の里資料館
──北前船の里資料館。
この集落の船主屋敷の典型的なスタイルで、通りに面して建つ町屋型ではなく、通りよりも後退したところに家屋が建つ農家型になっている。家屋は切妻造り妻入りの屋根がかけられ、そのまわりには下屋が設けられている。屋根は赤い瓦葺きで、棟には笏谷石が置かれて重しとなっている。そして、その家屋を囲んで塀の内側には土蔵が並び、武家屋敷のように風格のある構えになっていた。
「酒田と同じでね、この町も大火の被害に遭っているんだ」
資料館の正面で足を止め、幸成はそう語った。
「酒田よりもずっと前のことなんだけどね……」
橋立に大火があったのは明治五年のことだ。その際、多くの屋敷が燃え落ちてしまった。
「それじゃあ、ここもやはり、風が強い町なんですか?」
「うん。まぁ詳しいことはここのガイドさんにでも聞くといい。ちなみにこの資料館の元になっている酒谷家の屋敷も他の屋敷と同じく、大火のすぐ後、明治九年に再建されたものなんだ。敷地面積は一千坪近い。それでもね、酒谷家は橋立の北前商人としては、中レベルの財力しかないっていうから驚きだよ」
「なるほど。日本一の富豪村っていうのも、そんなに大げさな話じゃないんですね」
「うん。それじゃあ行こうか」
澪が正門横の事務所で見学の旨を告げると、待機していたガイド……ここでは語り部と呼ばれている……柿崎という、人懐っこそうな老人が案内をしてくれることになった。
「へぇ、酒田から。遠いところからようこそ。じゃあ早速、ご案内を。まず見て欲しいのは、この座敷に通じる正面の大戸です。柱に使われている欅や松もそうですが、これが当時のこの屋敷の繁栄の印なんです。この戸は秋田杉の一枚板なんですよ」
「これ、漆ですか?」
しっとりとした光沢の大戸を見て、澪は尋ねた。
「そうです。これ、漆を七回も八回も重ねて、だから今でも美しさを損なっていないでしょう? あ、そうだ。この材料の秋田杉も北前船で、秋田から直接、運ばれてきたものだといわれてます」
毎週金曜日更新 次回更新日:11/9

